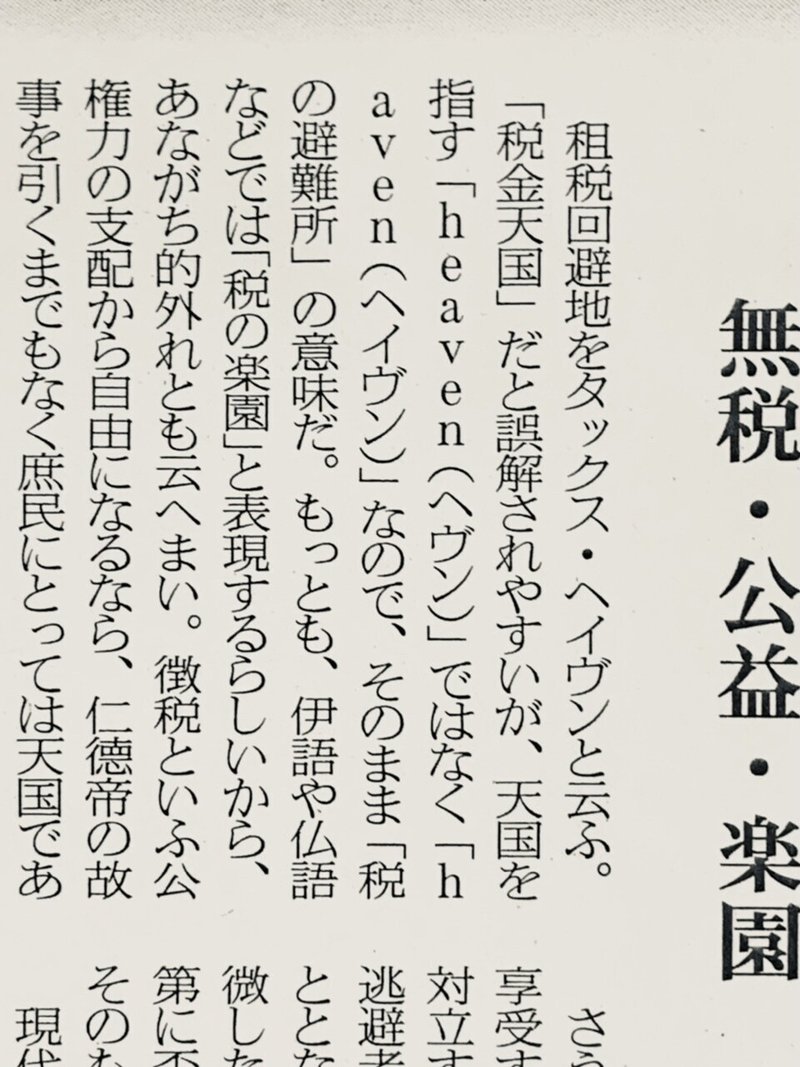植戸万典(うえと かずのり)です。またビアバーには行きづらい世相になってきて悲しみを覚えています。
ビール党です。日本酒も焼酎も洋酒もいける口ですが。
とくに所謂クラフトビール派でして、個人的には、最近は一時期ほどの持て囃されではないかもですけれどもヘイジーIPAとかが好物です。ただこう書くと、いやセゾンも良いしヴァイツェンも捨て難いしもちろんスタウトやポーターも美味しいしたまにはバーレーワインも飲みたくなってくるし……困ってしまいます。
ビール・クズです。
以下のコラムは、令和3年10月18日付の『神社新報』(「杜に想ふ」欄)に掲載されました趣味全開の「ビールに関する一考察」の再掲です。
歴史的仮名遣ひを現代仮名遣いに直しているのは敢えてですので、正仮名遣ひ派の方には悪しからず。
コラム「ビールに関する一考察」
ビールが美味い季節だ。否、訂正します。蒸し暑い日に飲み干す金色のピルスナーも、寒い夜にまったり味わう黒ビールも、大量にホップを使うIPAの苦味も、小麦ビールのフルーティーな爽やかさも、どれも美味い。要は、ビールはいつも美味い。
十月は日本酒の月と聞くが、ミュンヘンに由来のビールの祭典オクトーバーフェストで賑わうべき季節でもある。とくにこの十月は、各地で酒類の提供が再開され、酒徒にとって例年に増して喜ばしい月となった。めっきり足の遠退いている顔馴染みのビアバーにも、感染対策しつつぼちぼちと立ち寄りたい。
以前は地酒ならぬ「地ビール」と呼ばれたクラフトビールもこの十年で一般化し、また地域振興にも使われて、巷では「とりあえずビール」の様相だ。一部には社寺と連携したものもある。出来栄えの方はまぁさまざまにせよ、裾野の広がる分野はその山の頂も高くなり、多くの稔りを齎そう。
ビールに限らず、スポーツ、芸術、読書、食慾と、秋は何かにつけて好い時季であり、豊かな稔りの季節だ。なかでも米の稔りは、神話の時代から収穫の象徴だった。けれども今のような飽食の時代は、その価値も等閑視されがちかもしれない。
学界では、いつからか博士号を「足の裏の米粒」と云っている。その心は、取らないと気持ち悪いけど取っても食えない。
末は博士か大臣か、と子の将来を期待したのも昔の話。国による高等教育施策もあり、高学歴者が増えてアカデミアの裾野も広がる現代は、その一方で立場の不安定な研究員を量産することとなった。分野によって状況は異なるが、学位を得ても研究職は狭き門で、たとい就けても薄給且つ任期制では、研究の長期的展望も自身の人生設計も見通せまい。さりとて心機一転して企業就職するにせよ、なまじ高い学歴が目立って敬遠されることもしばしばだ。よほどの才能と運と覚悟がない限り、実家が太いか神経が太いかしなければ博士課程進学という決断は難しい、と院生の頃に思ったものである。そんな状況に実感の伴う諧謔が「足の裏の米粒」なのだ。
祭りで神前に供される米には農家の思いが籠もっているように、博士号という米粒にも本来ならば徒弟的に鍛えられた高度な技能が宿る。その高度な技能を支えている核心は、クラフトビールの「クラフト」にも託された職人の矜持に近いものがあるのではないか。
学問の秋は、そうした職人の入り口である大学院を志した学生が進学を決めている時期でもあろう。その職人への道は苦労も多いが、選んだ道中は少なくともひたすら学問に耽溺叶う代え難い時であることを、先達としては保証したい。そして何より論文を書き上げて飲むビールがまた格別なのだと伝えよう。
本稿の結論を纏めるなら、やはりビールはいつも美味い、ということである。(ライター・史学徒)
※『神社新報』(令和3年10月18日号)より